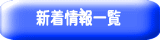「いや、それ違う」はもう古い? 令和の職場コミュニケーション
「いや、それは違うと思います」
「でも、前にも言ったよね?」
「そうは言っても、うちは無理だよ」
…こうした“否定から始まる”言葉、職場でよく聞きませんか?
もしかすると、あなた自身も無意識に使っているかもしれません。
もちろん、仕事には意見の違いや指摘がつきものです。
建設的な議論は必要ですが、「否定の言葉」から入るだけで、空気は一気に冷え込んでしまいます。
否定は「内容」より「入り方」が問題?
誰かの意見に異を唱えるとき、その内容が正しくても、伝え方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わります。
たとえば、
「でも、それは難しいですね」
と伝えるのと、
「その発想、面白いですね。そのうえで、現実的に考えると〇〇という課題がありそうです」
と伝えるのとでは、同じ指摘でも印象がまったく違います。
前者は“跳ね返された”感覚が残り、後者は“受け止めたうえで建設的に進めてもらえた”と感じられます。
「Yes, and…」の思考を取り入れる
即座に「No」と言う代わりに、一度受け入れてから自分の意見を重ねていく。
これは、即興演劇(インプロ)の世界で有名な「Yes, and」の手法にも通じます。
たとえば部下から「こういうやり方もありでは?」と言われたとき、
✗「いや、それは前に失敗した方法だよ」
〇「なるほど、そういう視点もあるね。そのときはうまくいかなかったけど、今なら工夫できるかもね」
少し言い換えるだけで、対話の可能性は広がります。
否定のクセは「思考のクセ」
否定的に返してしまうクセは、「完璧を求める」「先回りして問題を潰したい」という善意から来ていることもあります。
ただ、それがかえってチームの発想や提案を萎縮させてしまうこともあるのです。
・すぐに「いや」「でも」と言いそうになったら、一拍おいてから言葉を選ぶ
・相手の意見の「肯定できる部分」をまず探す
・違う意見でも、「立場」ではなく「内容」に目を向ける
この3つを意識するだけでも、職場の空気は穏やかに変わっていきます。
結局は、安心して話せるかどうか
誰かが何かを言うたびに否定される職場では、次第に発言する人が減っていきます。
逆に、「まずは聞いてもらえる」「意見を出しても大丈夫」と思える環境には、自然とアイデアや改善提案が集まります。
「否定しないこと」は、単に優しくするということではありません。
安心して意見を出し合える土壌をつくるための、第一歩なのです。
否定から入らない、その小さな意識が、信頼される職場づくりの第一歩になります。
明日の会話から、ほんの少しだけ言葉を変えてみませんか?