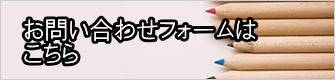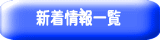辞めるときこそ、社員は見ている~退職対応で信頼を失わないために、会社ができること~

社員から「退職したいんですが…」と言われる瞬間。
どんなに人当たりの良い経営者でも、一瞬ドキッとするものです。
「思っていたよりショックだった」
「裏切られたように感じてしまった」
「今、このタイミングで言う?」
—これ、決して珍しいことではありません。
会社にとって退職者は、“これから一緒に進めない人”ですから、どうしても感情が動きます。
ただ、その気持ちのまま対応すると、ちょっと冷たくなってしまったり、必要以上に距離を取ってしまうことも……。
実はその“別れ方”こそが、会社の印象を決め、そして残された社員の士気や会社の未来にまで影響を与える分かれ道になるんです。
辞める人に冷たくしてしまうのは「自然な感情」
退職者に対して「辞めるならもう関係ない」と感じてしまうのは、ある意味、人間らしい反応です。
がんばって育てた人、信頼していた人が突然いなくなる。
「言い方が気に入らなかった」「恩知らずだ」と感じることもあるでしょう。
でも、そんなときこそ、ぐっと一呼吸。
感情をそのまま態度に出すのではなく、「どう送り出すか」に目を向けてみてほしいのです。
「引き止め」もまた、信頼を築くチャンス
退職の申し出があった際、会社として「ぜひ残ってほしい」と考えるのも自然な感情です。
特に、その社員が会社にとって重要な存在であれば、引き止めの検討は避けて通れません。
ただし、ここでも大切なのは、「感情的にならず、誠実に向き合うこと」です。
まずは、なぜ辞めたいのか、その理由に深く耳を傾けましょう。
不満や課題が社内にあるのであれば、それは会社改善の貴重なヒントになります。
その上で、なぜ会社に残ってほしいのか、その社員に何を期待しているのかを具体的に伝え、会社の状況や今後の展望を正直に話しましょう。
将来のキャリアパスや待遇改善など、会社としてできることを検討し、具体的な提案ができるとより説得力が増します。
引き止めを試みるプロセス自体が、残る社員たちに「会社は社員一人ひとりを大切にしている」というメッセージを伝える機会にもなります。
しかし、最終的には社員の意思を尊重する姿勢も忘れてはいけません。
たとえ退職に至っても、お互いにわだまりなく「円満」でいられることが、後の会社の評判や、もしかしたら再入社の可能性にも繋がるのです。
感情に流されず、「信頼」を築く送り出し方とは?
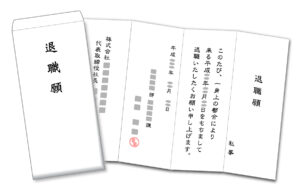
感情のコントロールは難しいもの。
だからこそ、感情に左右されない「対応の型」を持っておくことが大切です。
いわば「感情ではなく、仕組みで円満退職をつくる」という考え方。
この「型」は、感情を無視するものではなく、むしろ感謝や労いといったポジティブな感情を、確実に、そして適切に伝えるための道筋となります。
そのために、以下のような具体的な工夫があります。
①「退職届が出たら、まずこの面談」ルールで丁寧な対話を
「辞めるって言われて、ついキツい口調になってしまった」
「問い詰めるような感じになってしまった」
これは多くの現場で起きていることです。
そうならないように、退職希望者とまず最初に交わす“面談マニュアル”を作っておくのも有効です。
この面談の目的は、単に感情的な衝突を避けるだけでなく、本人の話に耳を傾け、会社としての感謝を伝えるための場を設けることにあります。
たとえば、![]() まず本人の話を遮らずに聴く
まず本人の話を遮らずに聴く![]() 「ありがとう」「おつかれさま」といった一言を、どのタイミングでも伝える
「ありがとう」「おつかれさま」といった一言を、どのタイミングでも伝える![]() 退職理由は掘りすぎない(強要しない)
退職理由は掘りすぎない(強要しない)
など、簡単なガイドラインを設けるだけでも、対応がぐっと丁寧になります。
② 手続きリストで「心の余裕」を生み出す
感情的なやり取りを防ぐには、「人の善意」だけで乗り切らないことも大切です。
退職時に必要な書類や手続きのチェックリストを用意しておくことで、「次に何をすればいいか」が明確になります。
これに沿って進めることで、「この人、辞めるのにあれもまだ渡してない!」という焦りや不満が出にくくなります。
これは単なる機械的な処理ではなく、会社の誠実さを可視化し、社員も会社も不必要な混乱なく、気持ちよく手続きを進めるためのツールなのです。
お互いの信頼関係を損なうことなく、スムーズな引き継ぎを促す効果もあります。
③「送り出しの場」は、残る社員へのメッセージ
「もう辞める人に送別の場なんて…」と感じる方もいますが、実はこれは“本人のため”だけでなく、“残された人のため”でもあります。
人が辞めていく姿は、他の社員が会社をどう見るかにも影響します。
ちゃんと感謝して送り出されたか、それともひっそりといなくなったのか。
その印象が、職場の空気にじわじわと影響を及ぼし、ひいては会社全体の士気や定着率にも関わってきます。
形式だけでも構いません。
最後に一言だけ、上司から「がんばったな」と伝えるだけでも違います。
感謝の気持ちをもって送り出す姿勢は、会社が社員一人ひとりを大切にしている証となり、社内文化の醸成に貢献するでしょう。
「終わりよければ、すべてよし」会社の未来を創る退職対応
退職対応を単なる「手続き」として片付けてしまうと、会社にとっても損なことが多いです。
感情的な対応や事務的すぎる流れが、あとから「不満だった」「冷たかった」という悪評につながるだけでなく、残された社員のモチベーション低下や、今後の採用活動への悪影響にも繋がりかねません。
社労士の立場から見ても、退職対応がうまくできていない会社は、残された社員のモチベーションや、今後の採用にも影響が出ていると感じます。
だからこそ、「冷たくなりがちなときこそ、仕組みで丁寧に送る」。
これが、会社の信頼を守る一番のポイントであり、退職者が「辞めた後も会社のファンでいてくれる」可能性を育むことにも繋がります。
最後に
退職の場面は、会社にとって一番“人間性”が問われるときです。
感情だけで対応してしまうのではなく、「信頼して送り出す仕組み」があることが、円満な職場づくりにつながります。
横山社会保険労務士事務所では、退職時の対応で「これってどうしたら…?」と迷う場面に寄り添いながら、必要な情報提供やアドバイスを行っています。
「もう辞める人なんだから…」ではなく、「辞めた後も会社のファンでいてくれる人」をひとりでも増やせるように。
そんな対応を、いまのうちから考えてみませんか?
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。