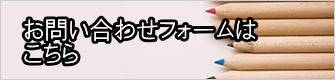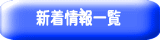【新規創業者向け】社労士って、結局どんなことを相談していいの?

会社を立ち上げたばかりの経営者の方とお話ししていると、こんな言葉をよく耳にします。
- 「社労士って、就業規則を作るときにお願いする人でしょ?」
- 「社員がまだ数人しかいないから、頼むほどじゃないですよね?」
- 「正直、どんなことを相談していいのか分からなくて…」
この“相談ハードル”はとても自然なものです。
社労士という存在は知っていても、実際にどんな場面で頼ればいいのか、具体的なイメージを持てない方が多いのです。
 創業者が実際によく抱える“素朴な声”
創業者が実際によく抱える“素朴な声”
まずは、実際に創業者の方からよく聞くリアルな声をご紹介します。
きっと「自分もそうだ」と思い当たるものがあるかもしれません。
 創業者の声①
創業者の声①
「最初に雇ったアルバイトさんとの契約、口頭で決めてしまったんです。
後から書面にした方がいいのかなと思いつつ、今さら言いづらくて…」
![]() こうした場面、実はよくあります。
こうした場面、実はよくあります。
社労士に相談していただければ、雇用契約書のひな型や説明の仕方まで、一緒に整理できます。
 創業者の声②
創業者の声②
「給与をどう計算すればいいか、ネットで調べても情報がバラバラで…。
残業代とか社会保険料のことも、正直不安で仕方ありません。」![]() ネット情報は一般論が多く、自分の会社にそのまま当てはめると誤解が生じやすいものです。
ネット情報は一般論が多く、自分の会社にそのまま当てはめると誤解が生じやすいものです。
社労士なら“自社の実情に合わせた方法”を具体的に示すことができます。
 創業者の声③
創業者の声③
「社員が『有給休暇を使いたい』と言ってきたけれど、会社としてどう対応するのが正しいのか分からなくて…。
間違えると不満につながる気がして、気軽に答えられませんでした。」![]() 労働基準法のルールを押さえていないと、ちょっとした質問にも答えにくいものです。
労働基準法のルールを押さえていないと、ちょっとした質問にも答えにくいものです。
社労士は、法律に基づいた対応を“かみ砕いて”アドバイスできるので、安心感が違います。
 よくある誤解と本当のところ
よくある誤解と本当のところ
社労士に関して、創業者の方が“つい信じてしまいがちだけれど、実は違う”という思い込みがあります。
そのままにしておくとリスクにつながることも少なくありません。
ここからは、特によく耳にする3つの誤解と、その本当のところをご紹介します。
 誤解①:社員が増えてからでないと必要ない
誤解①:社員が増えてからでないと必要ない
「まだ数人しかいないから」という理由で後回しにされがちです。
でも実際には、最初の数人をどう雇うかが、会社の“型”をつくる重要なタイミングです。
最初に整えておくことで、その後の人材採用や働き方のベースがぶれにくくなります。
 誤解②:相談内容は“制度づくり”に限られる
誤解②:相談内容は“制度づくり”に限られる
就業規則や人事制度はもちろん大事ですが、それだけではありません。
- 採用広告の出し方で気をつけること
- 面接で聞いてはいけない質問
- 給与や残業代の計算方法
- 保険や手続きの流れ
- 社員とのちょっとしたトラブル相談
こうした日常の細かいことこそ、創業期には頻繁に出てくるテーマです。
 誤解③:相談するには“きっちり準備”が必要
誤解③:相談するには“きっちり準備”が必要
「質問をまとめてからでないと相談しにくい」と思われる方も多いですが、実際は逆です。
漠然とした不安や、「これって大丈夫?」という小さな引っかかりをそのまま投げていただいて構いません。
むしろそこから掘り下げていくことで、思わぬ課題が早めに見つかることもあります。
 相談しなかったことで起きた“失敗談”
相談しなかったことで起きた“失敗談”
とはいえ「大丈夫だろう」と思って自己判断で進めてしまうのも、創業期にはよくあることです。
しかしその小さな判断が、後になって大きな問題になることがあります。
ここでは実際にあった“相談しなかったことで生じた失敗談”をいくつかご紹介します。
 事例①:残業代を払わなかったら思わぬ請求に
事例①:残業代を払わなかったら思わぬ請求に
創業まもなく、社員が3名ほどのA社。
「うちはまだ小さい会社だし、残業もほとんどないから、残業代なんて払わなくても大丈夫だろう」と、社長はつい軽く考えてしまいました。
数か月後、社員から「残業代は出ないんですか?」と指摘を受け、話し合いがこじれてしまいます。
結果として、過去の残業代をまとめて支払うことになり、資金繰りに大きなダメージが…。
![]() もし最初に社労士へ相談していれば、ルールを整えてトラブルを未然に防げたケースです。
もし最初に社労士へ相談していれば、ルールを整えてトラブルを未然に防げたケースです。
 事例②:雇用契約を口頭で済ませてトラブルに
事例②:雇用契約を口頭で済ませてトラブルに
B社では、知り合いをアルバイトとして採用しました。
「信頼しているし、細かい契約書なんて要らないよね」と口頭で条件を伝えただけで勤務を始めてもらったのです。
ところが、勤務日数や給与の支払い方法をめぐって食い違いが発生。
「そんな条件は聞いていない」と社員に言われ、揉め事に発展してしまいました。
![]() 雇用契約書を最初に交わしていれば、防げたトラブルです。
雇用契約書を最初に交わしていれば、防げたトラブルです。
社労士なら、会社に合った契約書の作成や説明方法をサポートできます。
 事例③:保険手続きを漏らしてしまった
事例③:保険手続きを漏らしてしまった
C社では、社員を初めて採用したときに、社会保険や労働保険の手続きを後回しにしてしまいました。
数か月後、役所から連絡があり「加入手続きがされていない」と指摘を受けることに。
結果として、未納分をまとめて納付しなければならず、予想外の出費と事務負担がのしかかりました。
![]() 社会保険・労働保険の加入は、社員を雇った時点で必須です。
社会保険・労働保険の加入は、社員を雇った時点で必須です。
社労士なら、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
 実際に社労士に相談できること
実際に社労士に相談できること
では、実際にどんなことを社労士に相談できるのでしょうか。
ここからは、創業者がよく依頼される3つの相談内容をご紹介します。
 採用から退職まで、従業員に関わる手続きをまるっとおまかせ
採用から退職まで、従業員に関わる手続きをまるっとおまかせ
従業員を雇い入れると、社会保険や雇用保険など複雑な手続きが必要です。
- 入社・退職時の資格取得や喪失手続き
- 毎月の給与計算や残業代の正しい計算
- 労働時間の把握や有給休暇の管理
こうした業務を自分で抱えるのは大きな負担。
社労士に任せることで、創業者は本業に集中できます。
 会社の成長を加速させる、就業規則と労務管理
会社の成長を加速させる、就業規則と労務管理
会社が大きくなるにつれて「言った・言わない」のトラブルは増えます。
その土台を固めるのが就業規則。
単なるルールブックではなく、会社の文化を言語化する大切なツールです。
また、労働時間管理や残業代計算といった日々の労務管理も重要。
専門家の視点でサポートを受けることで、安心して組織運営を進められます。
 従業員のモチベーションを上げる仕組みづくり
従業員のモチベーションを上げる仕組みづくり
「人が定着しない」「優秀な人材が来ない」という悩みは、多くの会社が抱えるものです。
社労士は人事評価制度や賃金制度の設計をサポートし、社員が生き生きと働ける仕組みを整えます。
- 正当に評価される人事制度
- 貢献度に応じた賃金体系
- キャリア形成を支える仕組み
これらが整うことで、社員のモチベーションが高まり、会社の成長を後押しします。
🔷まとめ
ここまでご紹介してきたように、創業者の方は「よくある誤解」や「ちょっとした自己判断」で思わぬリスクを抱えやすいことが分かります。
一方で、それらは社労士に気軽に相談することで、ほとんど未然に防ぐことができるのです。
日々の素朴な疑問や小さな不安も、遠慮なく相談していただいて大丈夫です。
例えば、
- 「こういう働き方を考えているけど、法的に問題ないかな?」
- 「社員に説明するとき、どんな言葉を使えばいい?」
- 「まだ会社が小さいうちに整えておくべきことは何?」
こうしたざっくりとした質問こそが、実は会社の成長に直結するヒントになるのです。
🔷社労士としてのひとこと
会社をつくるという挑戦は、毎日が初めてのことの連続です。
その中で「誰に聞けばいいのか分からない」と思ったとき、思い出してほしいのが社労士の存在です。
「大げさかな」と思うようなことでも大丈夫。
相談のハードルを下げていただければ、安心して次の一歩を踏み出せるお手伝いをさせていただきます。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。