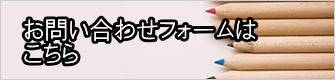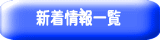就業規則を“毎年見直す会社”と“放置する会社”の差

~トラブル防止の観点から見直しのタイミングを具体解説~
「就業規則は一度作れば安心」
そう考えて、数年前に作ったままになっていませんか?
実はその油断が、思わぬトラブルを招くことがあります。
同じ業種・同じ規模の会社でも、“毎年きちんと見直す会社” と “何年も放置している会社” では、労務トラブルへの備えに大きな差が生まれているのです。
1.毎年見直す会社が得ている安心
就業規則を定期的に点検・改定している会社には、次のような「見えない安心」があります。
■ 法改正への確実な対応
労働関係の法律は、毎年のように少しずつ改正されます。
たとえば最近では――
- 育児・介護休業法の改正(男性育休の取得促進など)
- 労働時間の上限規制
- パート・アルバイトの社会保険加入要件の変更
など、企業規模を問わず影響を受けるものが多数。
見直しを怠ると、気づかないうちに違法状態に陥るリスクがあります。
■ 会社の実態に沿ったルール維持
働き方は年々変わっています。
テレワーク導入、副業制度の開始、評価制度の刷新など、社内の制度が動けば、規則も更新が必要です。
現状に合わない規則は、従業員から見れば「形だけのルール」。
実態と規則がかけ離れたした状態は、トラブルの火種になりやすいです。
■ トラブル時に会社を守る”盾”になる
いざ紛争が起こったとき、就業規則は会社の主張を裏付ける大切な根拠です。
最新の法律と実態に沿った規則は、労働基準監督署の調査や裁判の場で、会社を守る“盾”として機能します。
2.放置している会社が抱えるリスク
一方、長年手を入れていない就業規則には、次のようなリスクが潜んでいます。
- 法改正に未対応
「昔のままの残業規定」「古い休暇制度」などは、 労基法違反と指摘されれば罰則の対象にもなり得ます。 - 実態とのズレ
就業時間・休憩・手当など、実際の運用と違う内容が、規則に残っているケースは珍しくありません。
従業員が規則を根拠に請求してきた場合、会社が不利になることも。 - “無効”扱いになる可能性
規則の周知不足や、改正法に反する条文があると、その部分は効力を失う場合があります。
たとえば、
「休日出勤の割増率が古いままで未払い残業が発生」
「育休の取り扱いが法改正前の内容で従業員から改善要求」
といった事例は実際に起こっています。
規模の小さな会社ほど「うちには関係ない」と放置しがちですが、トラブルは会社の大きさを選びません。
3.見直しのベストタイミング
では、具体的にどのタイミングで見直せば良いのでしょうか。
ポイントは次の3つです。
(1) 法改正があったとき
最低賃金改定や育児介護休業法の改正など、労働法関連のニュースが出たタイミングは要注意。
「改正内容を踏まえて規則を変更する」ことが基本です。
(2) 会社の節目
テレワーク導入、評価制度の変更、新しい手当の創設、事業拡大など、働き方や人事制度に影響がある出来事があれば、その都度内容を確認しましょう。
(3) 毎年の定期点検
決算期や年度末など、会社の“振り返り”を行う時期に、年1回の棚卸しを習慣化するのがおすすめです。
「今年は改定不要」と確認するだけでもリスク軽減につながります。
4.“毎年見直す”という経営姿勢
就業規則を毎年見直すことは、単なる法令遵守にとどまりません。
- 従業員に対して「会社はルールを大切にしている」という安心感を与える
- 社内の制度や文化を定期的にアップデートする
- 経営者自身が働き方の変化をキャッチし続ける
こうした効果は、会社の信頼性そのものを高める投資でもあります。
🔷まとめ
就業規則は「作ったら終わり」の書類ではなく、会社と従業員を守る“生きたルール”です。
毎年見直している会社は、法改正や社内変化に強く、トラブルの芽を早い段階で摘み取ることができます。
逆に、何年も放置してしまうと、いざという時に会社を守れない――
これが最大のリスクです。
横山社会保険労務士事務所では、法改正情報のチェックから、実態に沿った改定案の作成まで、“会社の現場に寄り添った”就業規則の見直しをサポートしています。
「うちは何年も見直していないかも…」という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。