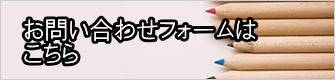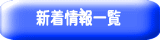就業規則でどこまで社員を縛れる?義務化の限界と会社側の注意点

~就業規則や社内規程でどこまで義務化できるか、実務での線引きを解説~
就業規則や社内規程を作るとき、よくある相談があります。
それは「社員にこれを守らせたいんですが、規程に書いておけば大丈夫ですか?」というものです。
しかし実際のところ、“書いておけば義務になる”という単純な話ではありません。
就業規則のルールには、大きく分けて2つの側面があります。
🔷「社員に守らせるルール」は“服務規律”や“業務命令”の範囲で
社員に守ってもらうルールとは、たとえば次のようなものです。
- 勤務時間中は私用スマホを使用しない
- 制服・身だしなみを整える
- 指示された業務を行う
- 遅刻・欠勤の際は事前に連絡する
これらはいわゆる服務規律にあたります。
会社が労働契約や業務命令の範囲内で、社員に求められる行動ルールを明確にしたものです。
ただし、ここには「合理的な範囲」という限界があります。
社員の私生活や思想信条に踏み込みすぎるようなルールは、たとえ就業規則に書いても効力が認められません。
たとえば「休日の過ごし方」や「交友関係」まで制限するような内容は、私人の自由を侵害するおそれがあります。
また「業務と関係のない誓約書を強制する」「SNSの私的発信を全面禁止する」なども、実務上はリスクが高いといえます。
社員に義務を課すときは、業務上の必要性と合理性があるかどうか。
この線引きがポイントです。
🔷「会社が守るルール」は“法令”と“就業規則”の両輪で
一方、会社自身にも守るべきルールがあります。
こちらは労働基準法をはじめとした法律に加えて、会社が自ら定めた就業規則や社内規程も含まれます。
つまり、就業規則は「社員を縛るもの」だけでなく、会社自身が守るべき約束ごとでもあるのです。
たとえば――
- 就業規則で「退職の申出は30日前までに」と書いたなら、会社もそのルールを前提に対応する必要がある
- 規程で「有給休暇の申請は1週間前までに」と定めたら、原則としてその運用を一貫して行わなければならない
- 賃金規程に「賞与を支給する」と明記している場合、経営判断で勝手にゼロにすることはできない
このように、「会社が自ら決めたルール」は、会社側の拘束力にもなります。
特に就業規則は、労働契約の一部として法的効力を持つため、軽い気持ちで変えたり運用をゆるめたりするのは危険です。
「会社は義務を果たそうとした」という決定的な証拠になります。
この手続きを怠ると、取得義務違反の責任を問われます。
🔷“義務化できる範囲”を考えるときの実務ポイント
就業規則や社内ルールを作るうえで、「ここまで義務にしていいのか?」という判断が必要になる場面は多いです。
その際に意識しておくと良いポイントを、3つ挙げます。
(1)目的が業務上の必要性に基づいているか
たとえば「制服着用」も、対外的な印象や安全衛生のためであれば合理性があります。
しかし「社長が好きだから」という理由では、義務づけの根拠が弱くなります。
(2)他の法令に抵触しないか
ルールによっては、個人情報保護法や労働安全衛生法、男女雇用機会均等法など、別の法律との整合性が必要です。
特に懲戒処分に関する定めは、過剰な内容だと無効になるリスクがあります。
(3)実際に運用できる内容か
「ルールはあるけど守られていない」「守らせると現場が回らない」――こうした規程は、結局“形だけ”になってしまいます。
規程を定めるときは、現場の実態に即しているか、運用が現実的かを必ず確認しましょう。
🔷まとめ:就業規則は「社員のため」でもあり「会社のため」でもある
就業規則や社内規程は、どちらか一方の立場を守るためのものではありません。
社員と会社の双方が、安心して仕事を進めるための“約束ごと”です。
社員にとっては「何を守ればいいのか」「どんな行動が評価されるのか」が明確になり、会社にとっては「どんな基準で判断・対応すべきか」が一貫します。
つまり、就業規則は“お互いの信頼を守るためのものさし”。
ここがあいまいなままだと、次のようなすれ違いが起きてしまいます。
- 社員:「昨日と言っていたことが違う」
- 会社:「何度言っても伝わらない」
このズレこそが、トラブルの温床になります。
本来、ルールとは“縛るため”のものではなく、“守り合うため”の仕組みです。
たとえば、
- 労働時間や残業のルールを明確にすることで、社員は安心して働ける
- 有給休暇の手続きや申請期限を定めることで、上司も部下も気まずさが減る
- 懲戒処分の基準を明文化することで、会社は公平性を保てる
このように「何が決まっているか」が明確であるほど、職場には安心感が生まれます。
逆に、「なんとなく」「今まではこうだった」で運用していると、人によって解釈が違い、最終的には「不公平感」や「モラルの低下」に繋がります。
そして、就業規則づくりの最終的な目的は、“社員が納得して守れる状態”をつくること。
どれだけ立派な規程でも、現場が理解していなければ形だけになります。
背景を説明し、現場の声を取り入れ、定期的に見直す。
この3つを意識するだけでも、ルールは生きたものになります。
就業規則は「作って終わり」ではなく、「会社の成長とともに育てていく」もの。
その視点を持つことで、ルールは“しばり”ではなく“信頼の基盤”へと変わります。
横山社会保険労務士事務所では、法律面の正確さはもちろん、現場で本当に使えるルール設計を重視しています。
「ここまで義務にしていい?」
「この規程、逆に会社のリスクになってない?」
そんな疑問が浮かんだときは、ぜひ一度ご相談ください。
ルールを“押しつけ”ではなく、“信頼を支える仕組み”として機能させる――
それが、横山社会保険労務士事務所が就業規則づくりで一番大切にしていることです。
ご質問やご相談は、お気軽に横山社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。