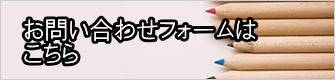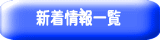“賃金台帳”ってどこまで書けばいいの?
「賃金台帳ってどこまで書けばいいの?」という質問を受けることがあります。
実際、Excelで管理している会社も多く、「給与明細を保存しているから大丈夫」と思っているケースも少なくありません。
でも、労働基準法上の“賃金台帳”は、実は明確な記載項目が定められており、単なる給与明細とは別物なんです。
🔷賃金台帳に「必ず」記載すべき項目

労働基準法第108条および労働基準法施行規則第54条では、次の事項を賃金台帳に記載しなければならないと定めています。
- 労働者の氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当などの種類とその金額
- 控除項目の種類とその金額
これらを見て「うちは給与明細で全部出してるからOK」と思われるかもしれません。
ですが、給与明細の形式が労基法上の“台帳様式”を満たしているかは別の話です。
特に、時間外や休日労働の時間数が抜けているケースが多く、監督署からの指摘ポイントになることもあります。
🔷Excel管理はOK? 電子保存は?
賃金台帳は紙で作る必要はなく、Excelなど電子データでの作成・保存も認められています。
ただし、条件があります。
労働基準法上の帳簿書類(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)は、以下のルールを満たす必要があります。
- いつでも出力できる状態で保存されていること
- 改ざん・削除の防止措置がとられていること
- 保存期間(退職後3年間)を満たすこと
つまり、Excelで管理する場合は「ファイルを共有サーバーやクラウド上で安全に保存し、過去の修正履歴を残す」などの対応が必要です。
特に複数人が編集できる環境では、“誰がいつ修正したか”がわかる状態を意識しておくことがポイントです。
🔷実務上のよくある落とし穴
(1)時間数の記録がざっくり
→ 「月の総労働時間」しか書いていないケースがありますが、時間外・休日・深夜ごとに区分する必要があります。
(2)通勤手当や住宅手当をまとめて「手当」と記載
→ 「手当の種類」を明示する必要があります。種類ごとの金額を明記しましょう。
(3)控除欄に「社会保険料」だけ
→ 健康保険・厚生年金・雇用保険など、控除の種類ごとに分けて記載が必要です。
(4)保存データの所在があいまい
→ パソコンの中だけ、USBだけ、というのはNG。第三者が確認できるように保管ルールを整備しましょう。
🔷Excelで作る場合のおすすめ構成
- A列:氏名
- B列:性別
- C列:賃金計算期間
- D列:労働日数
- E列:所定労働時間
- F列:時間外労働時間
- G列:休日労働時間
- H列:深夜労働時間
- I列以降:各種手当・控除項目
これに加えて「合計欄」「差引支給額」まで整理しておくと、給与明細との整合性も取りやすくなります。
🔷「形式よりも中身」が大事
監督署の調査では、形式そのものよりも「実態と整合しているか」が重要視されます。
出勤簿の時間と賃金台帳の時間が一致しているか、支給額が合っているか。
この“整合性チェック”がスムーズにできるようにしておくと、トラブル防止にもつながります。
🔷最後に:まずは「一度見直す」ところから
賃金台帳は、会社が社員の労働条件を正しく管理できているかを示す“土台”の記録です。
一度整えておけば、その後の労務管理や調査対応がぐっと楽になります。
「うちはExcelでやってるけど大丈夫かな?」
「給与ソフトの出力で足りてるのか不安…」
そんなときは、一度チェックしてみませんか?
横山社会保険労務士事務所では、現行の賃金台帳の確認や、Excelひな形の整備、電子保存のルールづくりまでサポートしています。
ご質問やご相談は、お気軽に横山社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
人を大切にする会社づくりを、記録の整備からサポートします。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。