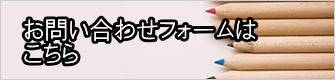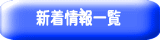🛡️ カスハラ(顧客からのハラスメント)から社員を守れ!企業の法的義務と具体的な対策

近年、「カスタマーハラスメント」、通称「カスハラ」が深刻な社会問題となっています。
これは、顧客や取引先などからの、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた、労働者の就業環境を害する言動を指します。
従業員の心身の健康と安全を守ることは、企業の最も重要な責務の一つです。
特に、2026年10月1日(予定)からは、カスハラ対策が法律により全ての企業に義務化されます。
この大きな変化に備え、企業が今すぐ取り組むべき法的義務と具体的な対策を解説します。
🔷企業の法的義務:改正「労働施策総合推進法」に基づく対応
2025年6月に改正が成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)により、カスハラ対策は、すでに義務化されているパワーハラスメント対策などと同様に、事業主の「雇用管理上の措置義務」として明確に位置づけられました。
📅 義務化の時期
施行予定日: 2026年10月1日(全ての企業が対象)
📝 企業に義務付けられる主な措置
企業は、カスハラを予防し、発生した際に適切に対応するために、以下の措置を講じることが義務となります。(パワハラ対策がベースとなる見込みです。)
1.方針の明確化と周知・啓発
![]() カスハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む全従業員に周知・啓発すること。
カスハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む全従業員に周知・啓発すること。
2.相談体制の整備
![]() 相談窓口を設置し、相談に適切に対応できる体制を整備すること。
相談窓口を設置し、相談に適切に対応できる体制を整備すること。
3.事後迅速かつ適切な対応
![]() カスハラ発生時、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者と行為者に対する適切な措置(懲戒処分など)を講じること。また、再発防止策を講じること。
カスハラ発生時、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者と行為者に対する適切な措置(懲戒処分など)を講じること。また、再発防止策を講じること。
4.プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止
![]() 相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いを禁止すること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いを禁止すること。
【ポイント】 この措置義務は、従業員数にかかわらず全ての事業主に適用されます。義務を怠り、国からの勧告に従わない場合は、企業名が公表されるリスクがあります。
🔷企業が取るべき具体的な対策
義務化を待つことなく、従業員を守り、企業のリスクを低減するために、今すぐ具体的な行動を起こしましょう。
1.予防・啓発のための対策(未然防止)
カスハラ防止の姿勢の明文化と周知
![]() 就業規則や社内規定にカスハラに関する定義、禁止事項、対応ルールを明記します。
就業規則や社内規定にカスハラに関する定義、禁止事項、対応ルールを明記します。
![]() 「暴言や不当な要求には応じかねる」旨を、店頭、ウェブサイト、掲示物などで顧客に向けても明示します。
「暴言や不当な要求には応じかねる」旨を、店頭、ウェブサイト、掲示物などで顧客に向けても明示します。
研修の実施
![]() 全従業員に対し、カスハラの定義、具体的な事例、初期対応、メンタルヘルスケアに関する研修を定期的に実施します。特に管理監督者には、部下からの相談対応や組織的対応について重点的に教育します。
全従業員に対し、カスハラの定義、具体的な事例、初期対応、メンタルヘルスケアに関する研修を定期的に実施します。特に管理監督者には、部下からの相談対応や組織的対応について重点的に教育します。
業務体制の整備![]() カスハラのリスクが高い業務(電話対応、窓口業務など)について、複数人体制での対応や、上司へのエスカレーションルールを明確にします。
カスハラのリスクが高い業務(電話対応、窓口業務など)について、複数人体制での対応や、上司へのエスカレーションルールを明確にします。![]() 通話録音装置や防犯カメラの設置、アクリル板などの物理的な防御措置も有効です。
通話録音装置や防犯カメラの設置、アクリル板などの物理的な防御措置も有効です。
2.発生時の適切な対応(事後対応)
対応マニュアルの作成![]() 「カスハラが発生したら誰が、どのように初期対応し、どの部署・役職に報告するか」といった具体的なフローを定めたマニュアルを作成します。
「カスハラが発生したら誰が、どのように初期対応し、どの部署・役職に報告するか」といった具体的なフローを定めたマニュアルを作成します。![]() 特に、「生命・身体の危険がある場合」、「不当な金銭要求・土下座要求などがあった場合」の対応(警察への通報など)を明確にします。
特に、「生命・身体の危険がある場合」、「不当な金銭要求・土下座要求などがあった場合」の対応(警察への通報など)を明確にします。
相談窓口の整備と機能強化![]() 社内だけでなく、社外の専門家(弁護士、産業医、外部相談窓口など)と連携した相談体制を構築し、従業員が安心して相談できる環境を整えます。
社内だけでなく、社外の専門家(弁護士、産業医、外部相談窓口など)と連携した相談体制を構築し、従業員が安心して相談できる環境を整えます。
被害者への配慮措置![]() 被害を受けた従業員に対し、産業医面談、メンタルヘルス休暇、配置転換などの適切な配慮措置を速やかに講じます。
被害を受けた従業員に対し、産業医面談、メンタルヘルス休暇、配置転換などの適切な配慮措置を速やかに講じます。
記録と証拠保全![]() カスハラの内容、日時、場所、対応者、経過などを詳細に記録し、音声や動画などの証拠を保全します。これが後の事実確認や法的措置の基礎となります。
カスハラの内容、日時、場所、対応者、経過などを詳細に記録し、音声や動画などの証拠を保全します。これが後の事実確認や法的措置の基礎となります。
🔷国の今後の対策と動向
カスハラ対策は、国の重要な政策課題として位置づけられています。法改正による義務化以外にも、国や自治体は多角的な対策を推進しています。
指針の策定![]() 厚生労働省は、改正法に基づき、企業が講ずべき具体的な措置の内容を定めた指針(ガイドライン)を今後策定・公表する予定です。企業はこの指針に沿った対策を講じる必要があります。
厚生労働省は、改正法に基づき、企業が講ずべき具体的な措置の内容を定めた指針(ガイドライン)を今後策定・公表する予定です。企業はこの指針に沿った対策を講じる必要があります。
自治体による条例制定![]() 東京都(2025年4月1日施行)をはじめ、都道府県や市町村レベルでカスハラ防止条例が制定・施行される動きが加速しています。中には、罰則付きの条例を検討している自治体もあります。
東京都(2025年4月1日施行)をはじめ、都道府県や市町村レベルでカスハラ防止条例が制定・施行される動きが加速しています。中には、罰則付きの条例を検討している自治体もあります。
支援措置の強化![]() 企業がカスハラ対策を講じるための奨励金や助成金の支給など、経済的な支援措置が国や自治体から提供される動きがあります。
企業がカスハラ対策を講じるための奨励金や助成金の支給など、経済的な支援措置が国や自治体から提供される動きがあります。
啓発活動![]() 社会全体でカスハラに対する意識を高めるため、国は「顧客と働く人が互いに尊重し合える社会」を目指し、広報や啓発活動を強化していく方針です。
社会全体でカスハラに対する意識を高めるため、国は「顧客と働く人が互いに尊重し合える社会」を目指し、広報や啓発活動を強化していく方針です。
🔷おわりに:カスハラ対策は企業価値向上のための戦略的投資
カスハラへの対応は、もはや「特定部署の一時的な問題」でも、「クレーム対応コスト」でもありません。
2026年10月の法的義務化を目前に控え、これは企業の持続可能性と経営戦略に深く関わるテーマとなっています。
🚀 人的資本経営とカスハラ対策
現在、企業の価値は「人的資本」によって測られる時代へと移行しています。
従業員がその能力を最大限に発揮できる環境を整備することは、企業にとって最大の競争優位性となります。
1.採用力の向上と離職率の低下![]() 従業員が守られていると感じる企業は、安心して働ける場所として評価され、優秀な人材の獲得に繋がります。逆に、カスハラが放置されている企業は、若年層を中心に敬遠され、人材流出のリスクが高まります。
従業員が守られていると感じる企業は、安心して働ける場所として評価され、優秀な人材の獲得に繋がります。逆に、カスハラが放置されている企業は、若年層を中心に敬遠され、人材流出のリスクが高まります。
2.生産性の向上![]() カスハラ被害は、従業員の心身の健康を損ない、モチベーションを著しく低下させます。対策を講じることで、従業員は心理的安全性を確保でき、業務に集中し、結果として生産性の向上に貢献します。
カスハラ被害は、従業員の心身の健康を損ない、モチベーションを著しく低下させます。対策を講じることで、従業員は心理的安全性を確保でき、業務に集中し、結果として生産性の向上に貢献します。
🌟 企業ブランドと信頼(信用)のリスク管理
カスハラへの対応姿勢は、企業のブランドイメージと社会的な信頼に直結します。
ポジティブな評価![]() 従業員を大切にする姿勢は、顧客や社会からの信頼を高め、企業イメージを向上させます。これは、「従業員ファースト」を訴求する強力なメッセージとなります。
従業員を大切にする姿勢は、顧客や社会からの信頼を高め、企業イメージを向上させます。これは、「従業員ファースト」を訴求する強力なメッセージとなります。
ネガティブなリスク回避![]() 対策が不十分な場合、カスハラが発生した際の対応のまずさがSNSなどで拡散され、炎上や不買運動に発展する可能性があります。法的義務化を背景に、対策不足は「法令遵守を怠る企業」という極めて大きな信用(信頼)の失墜リスクを招きます。
対策が不十分な場合、カスハラが発生した際の対応のまずさがSNSなどで拡散され、炎上や不買運動に発展する可能性があります。法的義務化を背景に、対策不足は「法令遵守を怠る企業」という極めて大きな信用(信頼)の失墜リスクを招きます。
🤝 求められる「顧客との新しい関係性」の構築
最終的に、カスハラ対策は、企業が目指す「顧客との関係性」を見直すことに繋がります。
企業は、過度な要求を許容することが真の顧客満足ではないことを明確にし、「顧客と働く人が互いに尊重し合える社会」の実現に向けた毅然とした姿勢を示す必要があります。
この姿勢は、良識ある顧客とのより強固な信頼関係を築く土台となります。
結びに
2026年10月からの法的義務化は、全ての企業にとってカスハラ対策を本格的にスタートさせる絶好の機会です。
これを単なるコストや義務と捉えるのではなく、「人的資本経営」を推進し、企業価値を向上させるための戦略的投資として、積極的な取り組みを進めていきましょう。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。