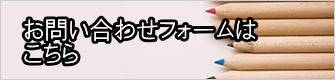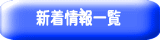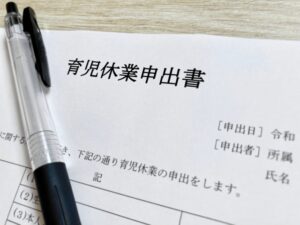就業規則が“あるだけ”になっていませんか?
~活用できる仕組みにするには~

「うちにも就業規則、ありますよ」
そうおっしゃる経営者の方は多いです。
でも、少し突っ込んで聞いてみると──
![]() 中身をちゃんと読んだことがない
中身をちゃんと読んだことがない![]() 入社時にも配っていない
入社時にも配っていない![]() 更新は何年も前のまま
更新は何年も前のまま![]() 何かあったときしか開かない
何かあったときしか開かない
そんな実態が見えてくることも少なくありません。
せっかく作った就業規則。
“あるだけ”ではもったいない!
トラブル予防にも、人材定着にも、活用しなければ意味がありません。
今回は、就業規則を「生きたルール」として機能させるポイントをお伝えします。
 なぜ「あるだけ」になってしまうのか?
なぜ「あるだけ」になってしまうのか?
理由はいくつかありますが、よくあるのがこの3つです。
![]() 専門用語が多くて読みづらい
専門用語が多くて読みづらい
→ 作成時に社労士任せにして、内容をあまり理解していないまま使われていることがあります。
![]() 社員に配布していない/説明していない
社員に配布していない/説明していない
→ 規則の存在を知らない社員もいて、トラブル時にも機能しません。
![]() 日々の運用ルールとズレがある
日々の運用ルールとズレがある
→ 実際の勤務実態と就業規則が合っていないため、現場で「使いにくい」状態に。
 活用できる就業規則にするための3ステップ
活用できる就業規則にするための3ステップ
 定期的に見直す(毎年チェックが理想)
定期的に見直す(毎年チェックが理想)
法律改正が頻繁にある昨今。
たとえば「育児・介護休業法」や「労働条件明示ルール」の改正など、知らない間に就業規則が“違法”な状態になっているケースも。
年に1回、内容を点検・見直す機会をつくりましょう。
特に次のようなタイミングでは要チェックです。
![]() 従業員数が増えたとき
従業員数が増えたとき![]() 就業形態(テレワーク導入など)が変わったとき
就業形態(テレワーク導入など)が変わったとき![]() 法改正があったとき
法改正があったとき
 社員に周知し、説明の機会をもつ
社員に周知し、説明の機会をもつ
就業規則は周知していないと効力が発生しません。
入社時にしっかり説明するのはもちろん、社内イントラネットや紙で誰でも見られるようにしておくことが大切です。
また、定期的に“こんなときはどうする?”といった社内研修やミニ勉強会もおすすめ。
「知らなかった」ことで起きるトラブルを未然に防げます。
 日々の運用とすり合わせる
日々の運用とすり合わせる
たとえば、こんなズレがないか見直してみましょう。
![]() 実際はフレックスタイム制なのに、規則は固定時間制のまま
実際はフレックスタイム制なのに、規則は固定時間制のまま![]() 有給休暇の運用が実態と異なる
有給休暇の運用が実態と異なる![]() 残業の申請ルールが明文化されていない
残業の申請ルールが明文化されていない
現場の声と規則の内容が合っているか?を確認し、必要に応じて調整を。
この「すり合わせ」が、就業規則を“絵に描いた餅”にしない最大のポイントです。
 よくあるご相談
よくあるご相談
![]() うちの規則、もう何年も見直していないけど大丈夫?
うちの規則、もう何年も見直していないけど大丈夫?
![]() 法改正への対応が追いついてないかも…
法改正への対応が追いついてないかも…
![]() 小さな会社でも就業規則って意味あるの?
小さな会社でも就業規則って意味あるの?
実は、小規模な企業ほど“明文化されたルール”が役立ちます。
「言った/言わない」「知らなかった」でのトラブルは、ルールと運用のズレから生まれます。
明確なルールは、経営者の時間と気力の“節約”にもなるのです。
ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ
「もしかして、うちも“あるだけ就業規則”かも…」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
「これって見直したほうがいい?」「法律の改正に対応できてるかな?」
そんなちょっとした疑問からで大丈夫です。
横山社会保険労務士事務所では、むずかしい言葉をかみくだいて、やさしくご説明いたします。
“使える就業規則”への第一歩、一緒に踏み出しませんか?
下の【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。お待ちしております。