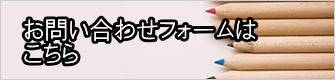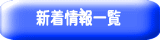「有給休暇」「代休」「振替休日」――混同しがちな3つの休日の違いと正しい取得のポイント

仕事の話で「休み」のことになると、よく「有給休暇」「代休」「振替休日」という言葉を聞きますよね。
どれも“会社を休む”という点では一緒ですが、実は意味も扱いも違います。
私も社労士として多くの相談を受けるなかで、会社も働く人もこの3つを混同して困っているケースをよく見かけます。
正しく理解しておかないと、トラブルのもとになることもあるので、今回はそれぞれの違いとポイントを丁寧に解説します。
 有給休暇(年次有給休暇)とは?
有給休暇(年次有給休暇)とは?
有給休暇は法律で定められた「働いた分の権利として給与が支払われる休み」です。
忙しい中でも“お金をもらいながら休める”というのは、働く人にとって本当に大切な権利。
だからこそ、有給休暇は労働者の意思を尊重して自由に取得できることが原則です。
![]() 会社の許可がなくても本人の希望で取得できる(ただし業務に支障がある場合は時季変更あり)
会社の許可がなくても本人の希望で取得できる(ただし業務に支障がある場合は時季変更あり)![]() 休んでも給与が支払われる
休んでも給与が支払われる![]() 労働基準法により会社は付与義務がある
労働基準法により会社は付与義務がある
 代休(代替休日)とは?
代休(代替休日)とは?

代休は、休日に働いた分を「後日に振り替えて取得する休み」です。
ここでのポイントは、労働基準法上、会社に代休を与える義務は規定されていないということです。
つまり会社が代休制度を設けている場合に取得できるものです。
私が相談を受ける中では、「休日出勤したのに代休がもらえなかった」という話も多く、トラブルになりやすい部分です。
代休は割増賃金の支払い義務も伴うため、運用ルールをあいまいにせず、就業規則や労使協定で明確にしておくことが重要です。![]() 休日出勤のあとに振り替えて休む
休日出勤のあとに振り替えて休む![]() 割増賃金の支払い義務がある
割増賃金の支払い義務がある![]() 会社に代休を与える法的義務はないが、制度運用のルールを決めておかなければならない
会社に代休を与える法的義務はないが、制度運用のルールを決めておかなければならない
 振替休日とは?
振替休日とは?
振替休日は「休日そのものを事前に別の日に移す」制度です。
例えば、本来の休日(例えば日曜日)に出勤しても、あらかじめ別の日(平日)を休日にすることで、休日労働とはせず割増賃金が発生しません。
ここで大切なのは、就業規則などに「休日を振り替えることができる」旨の規定を設けておくこと。
法律では、休日変更は事前に決めておかないと違法になるため、会社は透明性を持ってルールを整備しなければなりません。
私も「後から勝手に休日を変えられた」といったトラブルを多く見てきました。
事前に納得してもらうことが信頼関係の基本です。![]() 休日を前もって別の日に変更する
休日を前もって別の日に変更する![]() 割増賃金は発生しない
割増賃金は発生しない![]() 就業規則などに振替休日のルールを明記し、事前に決めておく必要がある
就業規則などに振替休日のルールを明記し、事前に決めておく必要がある
 まとめ:3つの休日の違いとポイント
まとめ:3つの休日の違いとポイント
![]() 有給休暇は、働いた分の権利として会社が必ず付与し、本人の希望により取得できる休み。休んでも給与が支払われる。
有給休暇は、働いた分の権利として会社が必ず付与し、本人の希望により取得できる休み。休んでも給与が支払われる。
![]() 代休は、休日に働いた分の代わりに後日休む制度。会社に与える義務はないが、割増賃金の支払いが必要なことが多いため、就業規則や労使協定で運用ルールを明確にすることが望ましい。
代休は、休日に働いた分の代わりに後日休む制度。会社に与える義務はないが、割増賃金の支払いが必要なことが多いため、就業規則や労使協定で運用ルールを明確にすることが望ましい。
![]() 振替休日は、休日を前もって別の日に移す制度。割増賃金は発生しないが、就業規則等に振替のルールを定め、事前に決めておくことが法律上必要である。
振替休日は、休日を前もって別の日に移す制度。割増賃金は発生しないが、就業規則等に振替のルールを定め、事前に決めておくことが法律上必要である。
 さいごに
さいごに
休日の扱いは会社と社員の信頼関係にも直結します。
私も実務で、こうした制度の誤解や運用のズレからトラブルになるケースを多く見てきました。
「うちの会社はどうなっているんだろう?」と思ったら、まずは就業規則や労働条件を確認してみてください。
横山社会保険労務士事務所はみなさんが安心して働ける職場環境づくりを全力でサポートします。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。