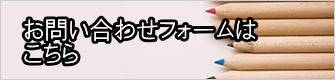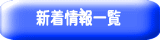【保存版】起業直後にやることリスト!社労士が伝えたい「3カ月の労務の基本」
社労士が教える「最初の3カ月」何すればいい?

こんにちは、社会保険労務士の横山です。
この春、会社を設立されたばかりの社長さま。おめでとうございます!
きっと今は、期待と不安が入り混じった忙しい日々を送られていることと思います。
「登記は済ませたけど、その後の手続きがよくわからない…」
「社会保険って、社員がいないうちは必要ないの?」
「雇用契約書って、ネットのテンプレートで大丈夫かな…」
そんな疑問や不安を抱えている方に向けて、会社設立から最初の3カ月で取り組んでおきたい“労務の基本”を、社労士の視点からわかりやすくまとめました。
 第1ステップ:社会保険・労働保険の「新規適用」は早めに!
第1ステップ:社会保険・労働保険の「新規適用」は早めに!
会社を設立したら、すぐに発生するのが「保険関係の手続き」です。
![]() 社員を雇った場合は「雇用保険」「労災保険」
社員を雇った場合は「雇用保険」「労災保険」![]() 役員報酬が発生している場合は「健康保険」「厚生年金」
役員報酬が発生している場合は「健康保険」「厚生年金」
これらは法律で定められた加入義務であり、放置していると後からまとめて加入させられたり、保険料をさかのぼって請求されたりするリスクがあります。
【チェックポイント】
- 従業員を雇う場合は、労災保険と雇用保険の両保険の加入手続きが必要です(ただし一定の条件を満たす場合は、雇用保険未加入でもOKです)
- 報酬が発生する場合は、原則として健康保険と厚生年金への加入が義務付けられています
- 手続きの窓口は「労働基準監督署」「ハローワーク」「年金事務所」などに分かれており、調べながら進めるのは意外と大変です
👉「手続きが複雑でわかりづらい」「開業準備で時間がとれない」という方は、社労士にご相談いただくことで、ミスなくスムーズに進めることができます。
 第2ステップ:就業ルールや雇用契約書を整える
第2ステップ:就業ルールや雇用契約書を整える
「小さな会社だから、そこまでしなくても…」
いえいえ、むしろ従業員が少ない時期こそ、トラブル防止の仕組みづくりが大切なんです。
![]() 勤務時間や休憩のルール
勤務時間や休憩のルール![]() 試用期間の有無とその取り扱い
試用期間の有無とその取り扱い![]() 残業代の計算方法や支払いのルール
残業代の計算方法や支払いのルール![]() 副業・兼業・SNS利用などの規定
副業・兼業・SNS利用などの規定
これらをあいまいにしたままスタートしてしまうと、後から「言った言わない」で揉める可能性が…。
【具体的な対策】
![]() 雇用契約書や労働条件通知書は、雇用時に必ず交付
雇用契約書や労働条件通知書は、雇用時に必ず交付![]() 社内ルールは「就業規則」にまとめておくと管理しやすい
社内ルールは「就業規則」にまとめておくと管理しやすい![]() 人数が10人未満でも、早めの整備がおすすめ
人数が10人未満でも、早めの整備がおすすめ
横山社会保険労務士事務所では、創業期の小さな会社向けに、コンパクトで実用的な就業規則のご提案も行っています。
 第3ステップ:給与計算と保険料の納付準備
第3ステップ:給与計算と保険料の納付準備
従業員を雇ったら、給与の支払いが始まります。
そしてそこからは、毎月の「社会保険料・雇用保険料」の計算と納付が待っています。
![]() 保険料は毎月変わる?固定?
保険料は毎月変わる?固定?![]() 会社と本人の負担割合は?
会社と本人の負担割合は?![]() どうやって納付すればいいの?
どうやって納付すればいいの?
給与計算ソフトに任せきりにしていると、保険料の金額や処理ミスに気づかないケースも。
【知っておくべきこと】
![]() 社会保険料は「翌月納付」
社会保険料は「翌月納付」![]() 雇用保険料率は年度によって変更があるため要確認
雇用保険料率は年度によって変更があるため要確認![]() 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度「年度更新」が必要
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度「年度更新」が必要
事業開始から3カ月も経てば、最初の給与支払い・納付・保険料通知など、実務面での「慣れ」が求められてきます。
手続きに不安がある場合は、外部のサポートも検討すると安心です。
 まとめ:最初の3カ月が、あなたの会社を支える“土台”になる
まとめ:最初の3カ月が、あなたの会社を支える“土台”になる
法人設立直後の数カ月は、勢いと情熱でなんとか乗り切れる期間です。
でも、「労務の基礎」をしっかり整えておくことが、あとから効いてきます。
![]() どこで、どんな手続きが必要?
どこで、どんな手続きが必要?![]() 雇用契約書や就業規則、どこまで整備すべき?
雇用契約書や就業規則、どこまで整備すべき?![]() 忙しくて手が回らない、誰かに相談したい…
忙しくて手が回らない、誰かに相談したい…
そんなときは、どうぞ横山社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
創業期のサポートはお任せください。
専門用語抜きで、わかりやすくご説明します。
📩 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ
新しいスタートには、不安も戸惑いもつきもの。
でも、ひとつずつ「正しく整えていく」ことで、会社は着実に前に進んでいきます。
横山社会保険労務士事務所は、そんな“はじまりの一歩”に寄り添う社労士事務所でありたいと思っています。
「こんなこと聞いていいのかな?」という内容でも大歓迎です。
どうぞお気軽にご相談ください。
あなたのスタートを、労務の面から全力でサポートします。
下記の【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。
(「会社設立後の手続きについて相談希望」と一言添えていただけるとスムーズです)
“ひとりではじめる”会社づくり、二人三脚でサポートいたします。