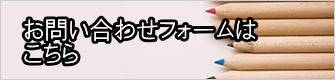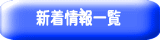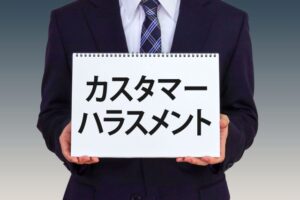法改正どうする?〜中小企業に必要な“ひと手間”とは〜
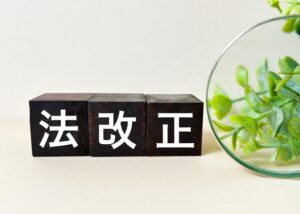
「また法律が変わったみたいだけど、うちは特に何もしてない」
「とりあえず書類だけ届いたけど、読んでない」
「誰かがなんとかしてくれるでしょ」
――そんな空気、ありませんか?
でも実は、法改正こそが「会社の足元を整えるチャンス」なんです。
うまく活かせば、働く環境が良くなったり、従業員の満足度が上がったり、トラブルの芽を早めにつぶせたりします。
逆に、何もせず放っておくと、「え、これ義務だったの?」と後から慌てることも…。
今回は、中小企業にとって本当に大切な“ひと手間”――
「法改正を自社に合わせて整理し、実行する方法」について、実務寄りにお話しします。
① 法改正は「概要」ではなく「自社でどう対応するか」で差がつく
労働・社会保険の法律の改正は毎年のようにあります。
厚労省のリーフレットやネットニュースでも情報は出回ります。
でも――そのまま“現場”に落ちてくることは、まずありません。
たとえば、最近の法改正をひとつご紹介します。
▽事例:月60時間超の残業割増率が「中小企業も1.5倍」に(2023年4月)
「うちはそんなに残業してないから関係ないよ」と思った社長も多いと思います。
でも、ある製造業の会社では、毎年繁忙期に月70時間前後の残業が常態化していました。
そのままにしていたら、ある社員から
「残業代が1.25倍で払われてますけど、本当は1.5倍じゃないんですか?」と指摘が。
→ 慌てて過去にさかのぼって差額を支払う事態に。
→ 残業代の追加コストだけでなく、社内の信頼感も一時的に失われました。
ポイントは、“関係ないと思っていた”ところに潜んでいたこと。
「法改正の概要」は知っていても、「自社の働き方に当てはめて考える」ところまで行けていなかったんですね。
② まずは「自社の実態と照らして考える」ことが第一歩
法改正に対応するために最初に必要なのは、
「これ、うちの会社だとどうなる?」と具体的に落とし込んで考えること。
たとえばこんな事例があります。
▽事例:育児・介護休業法の改正対応(2022年・2023年)
「男性社員が多いから、うちはそんなに関係ないと思ってた」
――という建設業の会社。
でも実際には、現場スタッフのうち、30代の既婚男性が複数在籍。
奥様が妊娠中という社員もいて、出生時育休(いわゆる“産後パパ育休”)の対象に。
対応をしないまま迎えてしまった結果、本人からの「休みたい」という申し出に慌てて規程を探す…という状態に。
→ 本来は制度を利用できたにもかかわらず、会社が十分な説明をしなかったため、社員は育休を取らずに働き続けました。
→ 「制度があるならちゃんと説明してほしかった」と不満が残りました。
表面的に「関係なさそう」と思うだけで判断すると、実際にはリスクを見落としてしまう。
そんな場面が少なくありません。
③「全部完璧にやる」より、「対応の順番を決める」
中小企業には人手も時間も限界があります。
だからこそ、優先順位をつけて取り組むことが大切です。
おすすめは、次の3ステップでの対応です。
![]() 1.法改正の「概要」を押さえる
1.法改正の「概要」を押さえる
→ これは社労士や業界団体からの情報で十分です。
![]() 2.“自社に関係ありそうなもの”だけピックアップ
2.“自社に関係ありそうなもの”だけピックアップ
→ 従業員数、年齢層、雇用形態、業種特性を軸に。
![]() 3.関係がありそうなものから順に、「現状との差」を確認
3.関係がありそうなものから順に、「現状との差」を確認
→ 規程はどうなってる?運用は?書式はある?など。
▽事例:労働条件明示のルール変更(2024年4月)
ある建設業の会社では、
・雇用契約書は紙で作成
・更新条件や就業場所は都度口頭で説明
という運用をしていました。
2024年4月からは、「就業場所・業務内容の変更範囲」などの明示義務が追加。
また、有期契約では「更新上限の有無」も必須に。
社内では「いっぺんに変えるのは大変」という声もあり、まずは、
- 新規雇用契約から優先的に新ルールを反映
- 次に、更新時の契約に順次適用
- 最後に、パートタイマーなど短時間契約にも拡大
と、段階的に進めていきました。
「どこからやるか」「どう進めるか」を分けて考えることで、無理なく対応できる道が見えてくることもあります。
整理すること自体が、実はとても大切な第一歩
法改正の対応は、どうしても「やらなきゃいけないことリスト」が膨大に見えてしまいがちです。
だからこそ、何から手をつけてよいかわからず、つい先送りしてしまう。
でも、私は社労士として日々企業の相談を受ける中で感じるのは、
「まずは自社の状況を正しく把握して整理すること」自体が、すでに大きな前進になるということです。
整理をすることで、
・今すぐ対応が必要なこと
・今はまだ様子見でいいこと
・そもそも誤解していたこと
…が見えてきます。
それは会社にとって、
「不安や漠然とした焦り」を減らし、
「やるべきことと優先順位」がクリアになる瞬間です。
そしてその整理は、社労士が全面的にサポートできる部分でもありますが、
会社自身が一度立ち止まって考えるだけでも、確実に変化が起きます。
最後に
私は、法改正への対応を「会社が抱える複雑さを整理し、実務に落とし込むための一助」として捉えています。
中小企業の皆さんにとって、法律の変化はしばしば負担や不安の種になりがちです。
ただ、だからこそ「全部完璧にやろう」と頑張りすぎず、
「今の自社に必要なことを見極めて、段階的に進める」ことが大切だと感じています。
そのための“情報の整理”や“優先順位づけ”は、私たち社労士が普段の相談の中で、最もご支援しやすい部分です。
決して難しく構えず、まずは自社の現状を確認すること。
そこから少しずつ、一緒に歩みを進めていければと考えています。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。