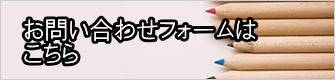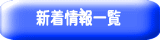社会保険って必ず入るもの?~法人成りした新規創業者が知っておくべき社会保険の加入義務と手続き~
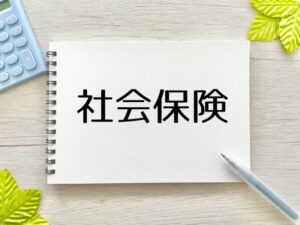
「これからは法人として、もっと事業を大きくしていきたい――」
そう決意して、法人成りという一歩を踏み出した(踏み出そうとしている)社長さんも多いのではないでしょうか。
新しいステージに進むというのは、とても勇気のいることですよね。
ただ、法人になるとどうしても避けて通れないのが、「社会保険の加入」という手続きです。
「え、うちって入らなきゃいけないの?」
「社長だけでも加入が必要?」
「どこでどう申請するの?」
そんなふうに戸惑っている方は、本当に多くいらっしゃいます。
社会保険の話って、なんとなく難しそうで、
つい「あとで調べよう…」と後回しにしたくなる気持ちもすごく分かります。
でも――
制度のことを知っておくと、「いまやるべきこと」「自分を守る仕組み」がちゃんと見えてくるんです。
この記事では、法人成りされたばかりの方(これから法人成りを予定している方)向けに、社会保険の加入義務や手続きの流れ、そして実際のメリット・デメリットについて、社労士の視点からやさしく解説します。
法人になったら社会保険は原則「強制加入」
個人事業主の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は任意(一部例外あり)ですが、
法人を設立すると、従業員の有無にかかわらず、原則として社会保険への加入が義務付けられます。
これは、たとえ社長一人だけの会社であっても同じです。
「社会保険」と聞くと、従業員を雇った時に加入するもの、というイメージがあるかもしれませんが、社長自身も会社の役員として社会保険に加入することになります。
なぜ強制加入なの?
社会保険は、病気やケガ、老齢、障害、死亡といった「もしも」の時に、加入者とその家族の生活を保障するための大切な制度です。
法人として事業を行う場合、従業員の生活を守る責任が生じるため、社会保険への加入が義務付けられているのです。
加入が必要な社会保険の種類
法人が加入する社会保険(広義)は、主に以下の4種類です。
- 健康保険 :医療費の自己負担を軽減するための保険です。
- 厚生年金保険:老後の生活を保障するための年金制度です。
将来受け取る年金額は、国民年金のみの場合よりも手厚くなります。 - 雇用保険: 従業員が失業した際の生活保障や、育児休業給付、介護休業給付などの制度です。
役員のみの法人の場合、原則として雇用保険の加入はできません。 - 労災保険: 従業員が業務中や通勤中に事故に遭ったり、病気になったりした場合に保障する保険です。
こちらも役員のみの法人の場合、原則として労災保険の加入はできません。
健康保険と厚生年金保険は「狭義の社会保険」と呼ばれ、雇用保険と労災保険は「労働保険」と呼ばれて区別されることもあります。
法人成りした場合、特に健康保険と厚生年金保険の加入が最重要となります。
社会保険加入のメリット・デメリット
法人成りして社会保険に加入することには、それぞれメリットとデメリットがあります。
メリット
![]() 社会的な信用度の向上: 社会保険に加入していることは、企業としての信頼性を示す一つの指標となります。
社会的な信用度の向上: 社会保険に加入していることは、企業としての信頼性を示す一つの指標となります。
![]() 将来の保障の手厚さ: 厚生年金に加入することで、国民年金のみの場合と比較して、将来受け取る年金額が増加します。
将来の保障の手厚さ: 厚生年金に加入することで、国民年金のみの場合と比較して、将来受け取る年金額が増加します。
![]() 万が一の際の安心: 病気やケガ、出産などで働けなくなった場合、傷病手当金や出産手当金が支給されるなど、いざという時の保障があります。
万が一の際の安心: 病気やケガ、出産などで働けなくなった場合、傷病手当金や出産手当金が支給されるなど、いざという時の保障があります。
![]() 優秀な人材の確保: 従業員にとっても、社会保険が完備されていることは働く上での安心材料となり、人材確保の面でも有利に働きます。
優秀な人材の確保: 従業員にとっても、社会保険が完備されていることは働く上での安心材料となり、人材確保の面でも有利に働きます。
デメリット
![]() 保険料負担の発生: 会社と従業員(役員含む)で折半して保険料を負担する必要があり、会社の経費が増加します。
保険料負担の発生: 会社と従業員(役員含む)で折半して保険料を負担する必要があり、会社の経費が増加します。
![]() 経理処理の複雑化: 社会保険料の計算や納付など、経理業務が増えることになります。
経理処理の複雑化: 社会保険料の計算や納付など、経理業務が増えることになります。
![]() 手続きの煩雑さ: 加入手続きや、従業員の入社・退社時の手続きなど、行政への届出が必要になります。
手続きの煩雑さ: 加入手続きや、従業員の入社・退社時の手続きなど、行政への届出が必要になります。
社会保険加入の手続きの流れ
社会保険の加入手続きは、主に以下の流れで進めます。
(1) 年金事務所への届出
法人設立後5日以内に、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを提出します。
(2) (従業員を雇用する場合)ハローワーク・労働基準監督署への届出
従業員を雇用する場合は、ハローワークで雇用保険、労働基準監督署で労災保険の加入手続きを行います。
これらの手続きには、登記簿謄本や法人設立届出書の控えなど、様々な書類が必要になります。
また、期限が設けられているものも多いため、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
近年はオンラインでの手続きも進んでいますが、初めての方にはやはり窓口での確認や専門家のサポートを受けることが安心です。
各機関の連絡先や窓口の場所は、設立時にしっかり確認しておきましょう。
(3) その他の注意点
社会保険は、加入したら終わりではありません。
役員報酬の変更や従業員の給料の増減があった場合には、保険料の見直しや必要な変更届の提出が求められます。
また、毎年「算定基礎届」の提出や、従業員の入社・退社に伴う「資格取得届」「資格喪失届」などの手続きも忘れずに行う必要があります。
こうした継続的な管理を怠ると、保険料の計算ミスや未届けによるトラブルにつながるため、定期的に確認し、適切に対応することが大切です。
個人事業主時代の国民健康保険・国民年金はどうなる?
法人成りして社会保険に加入すると、個人事業主時代に加入していた国民健康保険と国民年金は、原則として脱退することになります。
- 国民健康保険: 新たに加入する会社の健康保険に切り替わります。
- 国民年金: 厚生年金に加入するため、国民年金の第2号被保険者となり、国民年金の保険料を個別に納付する必要がなくなります。
まとめ
法人成りした会社にとって、社会保険への加入は「義務」です。
だからこそ、「よく分からないけど、なんとなく手続きした」ではなく、意味を理解しながら、自分ごととして取り組んでほしい――そう思っています。
制度って、どうしても“固くて難しいもの”に感じられがちですが、その中には、社長ご自身やご家族、そしてこれから関わる人たち(従業員)を守る仕組みが詰まっています。
毎月の保険料も、仕組みを知ることで「未来への備え」「会社の信頼性」につながると感じられるはずです。
私は、制度をただ説明するだけの人ではなく、「不安や疑問を整理する相手」になりたいと思っています。
難しいことをかみ砕いて、一緒に納得しながら進めていく。そんな存在でありたいと願っています。
分からないこと、気になることがあれば、どうぞ気軽にお声がけください。
制度が味方に思えるようになったとき、きっと事業への向き合い方も、少し変わってくるはずです。
ご相談は下記の【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。