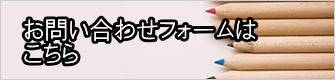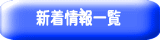「最初の1人」を雇う前に読んでおきたい、採用と労務のはじめの一歩
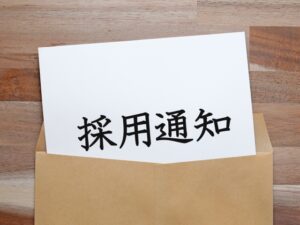
事業が少しずつ軌道に乗りはじめ、「そろそろ人を雇いたい」と思ったとき。
それは、事業の成長を実感できるうれしい瞬間でもあります。
けれど、初めての採用には、思っている以上にたくさんの「準備」が必要です。
今回は、創業まもない事業者さんが「最初の1人」を雇う前に知っておきたいポイントを、やさしく解説します。
 そもそも「雇用」とは?
そもそも「雇用」とは?
「誰かに手伝ってもらう」ことと、「雇用契約を結ぶ」ことは、実はまったく違います。
労働時間、業務内容、賃金の支払い義務、社会保険など…法律的な責任が発生します。
たとえパートやアルバイトであっても、雇えば「労働者」としての権利が発生するのです。
「ちょっとした仕事だし、知り合いにお願いしただけ」という軽い気持ちが、のちのトラブルの火種になることも。
まずは「雇う」という行為そのものの意味を、正しく理解しておくことが第一歩です。
 「労働条件」って、どこまで決めておくべき?
「労働条件」って、どこまで決めておくべき?
いざ採用となったとき、どんな条件で働いてもらうか――それをしっかり決めておくことが、トラブル予防の第一歩です。
勤務時間や休日、時給や交通費など、曖昧なままではあとで「聞いてなかった…」というすれ違いが起きがち。
まだ雇っていなくても、「どんな形で働いてもらうのか」を紙に書き出してみるだけでも、見えてくるものがありますよ。
 社会保険・労働保険の加入義務をチェック
社会保険・労働保険の加入義務をチェック
「まだ1人だから必要ないよね?」と思っていませんか?
実は、常時1人でも“法人”なら原則社会保険は必須。
また、個人事業主でも雇用状況によっては労災保険や雇用保険の加入が必要になります。
この判断を誤ると、後からさかのぼって加入手続きや保険料の納付を求められるケースも。
不安なときは、労働局や社労士に確認するのがおすすめです。
 時間とお金のルールを、曖昧にしない
時間とお金のルールを、曖昧にしない
「残業ってどれだけしてもらっても大丈夫?」「給与は末締め翌月払いでいいの?」
こうした基本的なルールを、なんとなくで決めてしまうと、のちの混乱や不満の原因になります。
小さな会社でも、時間外労働や休日出勤の扱いは重要です。
トラブルが起きたとき、「最初にちゃんと決めておけば…」と後悔する方も少なくありません。
 就業規則は“まだ早い”ではない?
就業規則は“まだ早い”ではない?
「まだ数人しかいないから、就業規則はそのうちで…」と思っている方も多いかもしれません。
でも、最初の1人を迎え入れる段階で、会社の方針やルールを整理するのはとても効果的です。
ミニマムな就業規則からスタートし、従業員が増えたら段階的に整備していくことも可能です。
最初から完璧を目指さず、まずは“軸”をつくることが大切です。
 「助けてもらう」から「チームになる」へ
「助けてもらう」から「チームになる」へ
雇うということは、仕事を分担するというだけではなく、「人と一緒に働く責任」を持つこと。
最初の1人との関係が、その後の組織づくりの土台になることも少なくありません。
「ちょっと手伝ってもらう」ではなく、「一緒に育つ仲間になる」つもりで、雇用を考えてみましょう。
育てること、任せること、その積み重ねが“チーム”になっていくのです。
おわりに ~最初の一歩を、焦らずていねいに~
最初の1人を迎えるとき、少し肩に力が入ってしまうかもしれません。
でも、あわてて雇ってしまうより、今のタイミングで「労務の基礎」を整えることが、未来の安心につながります。
「うちの場合はどうしたら…?」と迷ったときには、ひとりで抱え込まず、外部の専門家(社労士)に相談することも選択肢のひとつです。
💬 横山社会保険労務士事務所では、最初の採用に関するご相談も承っています。
「何から始めたらいいかわからない」
「自分で調べてみたけど、不安が残る」
そんなときは、お気軽にお問い合わせください。
小さな会社の“はじめの一歩”を、ていねいにサポートいたします。
👉 下の【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。