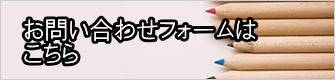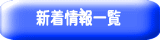【給与明細に書いてあるのに…?】それ、伝わっていないかもしれません
今回は、「給与明細に書いてあるのに『知らなかった』と言われる件」についてお話しします。
これは実務の現場でよくある“あるある”であり、労務トラブルの芽になるテーマでもあります。
明細に書いてある=伝わっている、とは限らない
給与明細は、労働基準法第24条の定めに基づき、賃金を明確に支払うための重要な書類です。
控除の内訳や各手当の支給額も、法令上「本人に明示」されていなければなりません。
しかし実際のところ、「明細に記載している」だけでは、従業員に内容が伝わっていないケースも少なくありません。
【実例1】通勤手当を「もらっていない」と勘違い
ある企業でのこと。
入社したばかりの従業員が、「通勤手当はつかないんですか?」と人事に尋ねてきました。
でも実際は、通勤手当(月額上限2万円)がしっかり支給されており、明細にも「通勤手当:¥15,000」と明記されていたのです。
詳しく聞いてみると、「交通費」という名目で別途もらえると思っていたそうで、給与と一体で振り込まれていることに気づいていなかったとのこと。
→ 法的には支給・明記されていても、“伝わっていない”ことで誤解が生まれた一例です。
【実例2】時間外手当の支払い月を巡る誤解
別のケースでは、従業員から「先月の残業代がついていない」と相談がありました。
よく確認すると、締日が月末、支払日が翌月15日のため、たとえば5月に行った残業は翌月の6月支払いの給与に反映される仕組み。
会社としてはなんの問題もない処理でした。
しかし従業員側は、「残業した月の給料に入っているはず」と思い込んでいたため、「未払いでは?」という誤解につながったのです。
→ 労基法上は支払期日に間に合っていれば問題ありませんが、「どの月の労働分か」を説明することは信頼形成につながります。
【実例3】住民税の金額が増えていた理由
6月になるとよくあるのが、住民税の金額変更に関する問い合わせ。
住民税は前年の所得に基づいて市区町村が課税するもので、毎年6月に新しい金額に切り替わります。
しかし、その仕組みを知らない方にとっては、給与明細を見て「いきなり引かれる額が増えた!」と驚かれることも多いです。
→ これも法律に基づく適正な控除であっても、制度を知らなければ不信感につながる典型例です。
「書いてあるから伝わっている」は、会社側の思い込みかも
給与明細は、確かに記録としては大切ですが、「伝える手段」としては一方通行になりがちです。
・社保の等級変更による保険料アップのとき
・手当の支給要件が変わったとき
・退職にともなう最終給与が支給されたとき
など、“少しの説明”があれば誤解を防げる場面はたくさんあります。
社労士からの提案:「ひとことメモ」を添える工夫
実務上よくおすすめしているのが、給与明細に小さな「ひとことコメント」をつける工夫です。
たとえば:
・「今月より新しい住民税額が適用されています」
・「今月より時間給の単価が変更になっています」
・「通勤経路変更届に基づき通勤手当を変更しました」
ちょっとしたひと手間ですが、従業員とのコミュニケーションコストを大きく減らす効果があります。
まとめ:給与明細は“説明責任”の出発点
給与は、労使間で最もトラブルになりやすいポイントのひとつ。
そのなかで給与明細は、法令遵守の証拠であると同時に、従業員への説明責任の第一歩でもあります。
「うちは明細に全部書いてるから大丈夫」と安心するのではなく、“どう伝えるか”にも目を向けてみてください。
横山社会保険労務士事務所からのご案内
制度やルールを「書いて終わり」にしない。
横山社会保険労務士事務所では、そんな労務管理をお手伝いしています。
・賃金規程・就業規則の見直しと、実務への落とし込み
・給与明細に関する従業員からの疑問・不満の相談対応
・勘違いを防ぐための説明文やQ&Aの整備サポート
「伝わっているつもり」が誤解を生む前に。
小さな違和感やモヤモヤを見逃さない社内環境づくりを、一緒に考えていきます。
👉お問い合わせは、下の【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。